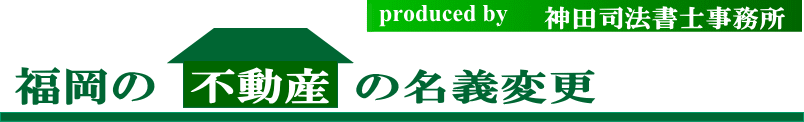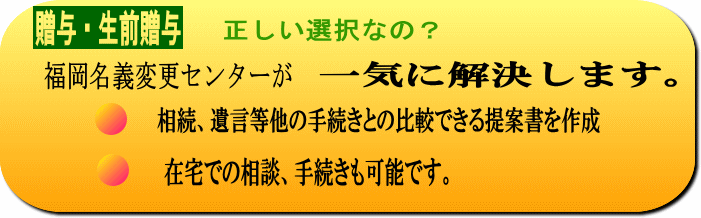
贈与、生前贈与には、多くの専門知識が必要です。
法律、税金の知識が必要なことはもとより、本当に適切な手続きなのか否かを判断するには、経験に基づくノウハウが必要不可欠です。
当センターによる贈与、生前贈与の特徴は、以下の通りです。
1.遺言等の他の手続きと比較した提案書を作成いたします。
2.お客様のお話をゆっくりお聞きし、お客様に最も適した手続きをご提案します。
3.在宅での相談、手続きも可能です。
福岡の神田司法書士事務所は、失敗しない贈与、生前贈与のためのノウハウがあります。是非、当事務所にお電話いただければと思います。
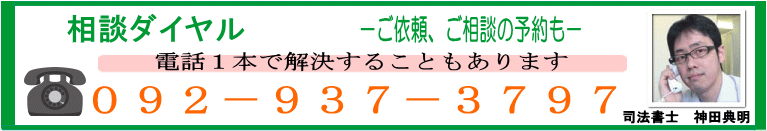
贈与の基礎知識
■不動産の名義変更をするには、必ず理由が必要になります。
特に理由がないという場合は、「贈与」が原因となります。
■贈与は、無償で財産を譲渡する契約ですが、贈与契約は諾成契約であり、贈与をする人、贈与を受ける人の口約束だけで成立します。
しかし、口約束による贈与は、不動産であれば引渡し、登記が終了するまでは契約は撤回することが可能です。契約書を作成しての贈与は、契約の時点で原則撤回することはできません。
■前記のとおり諾成契約なのですが、贈与をされる場合は、契約書は必須になります。
贈与に基づいて不動産の登記の名義変更をする際には、契約書を登記の添付書類として法務局に提出しなければなりませんし、贈与があったことを証拠として遺す必要があるからです。
生前贈与とは?
■生前贈与とは、一般的に相続対策として、特定の人に財産を承継させる必要がある場合に、生前に贈与しておくことです。
■生前に贈与せずに遺言書を書くことによっても同じ目的を達することができますので、どちらの手続を選択するかが問題となりますが、経済的な面や状況により選択する必要があります。
生前贈与の問題点
■生前贈与には、いくつかそれを行なうについてクリアすべき問題点があります。
1.贈与税
~~贈与税の基礎知識~~
■誰かに財産を無償で譲り渡す(=贈与する)場合、原則として贈与税がかかります。
■納税義務者は、受贈者(譲り受けた人)です。
■贈与税は、基礎控除が年に110万円あります。
つまり、年間110万円を超えなければ、課税されません。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※計算方法例・・・1000万円の不動産を贈与した場合
1000万円-110万円(基礎控除額)=890万円(基礎控除後の課税価格)
890万円×40%-125万円=231万円(贈与税額)
■上記のように贈与税は、とても高額です(相続税に比べてもはるかに高額です)。
基本的に、生前贈与する場合は、贈与税のかからない形で行なう必要があります。
■贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
~~夫婦間贈与の特例の利用~~
■婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)する特例があり、それを利用すれば、2110万円以内の不動産であれば無税で贈与することができます。
【特例を利用できる要件】
a.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
b.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
c.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
【申告】
■この特例を受ける場合でも贈与税の申告が必要です
(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)。
■申告に必要な書類
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
※ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要。
~~相続時精算課税制度の利用~~
■相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの。)
に対する贈与について、贈与時に贈与税を支払い、その後、相続時に贈与財産と相続財産とを合計し、計算した相続税額からすでに収められた贈与税額を差し引いて支払う制度です。
この制度は、暦年課税との選択になりますので、相続時精算課税を利用すると、暦年課税は使えなくなります。
ここまでお読みいただいただけでは、どうして贈与税の対策になるか分からないと思われるでしょうが、重要なのはこれからです。
相続時精算課税制度を利用した贈与には、特別控除額が2500万円あります。
つまり、2500万円以内の不動産であれば贈与税はかからないのです。
2500万円を超えた部分につきましては、一律20%の税率で贈与税を支払いますが、相続時の相続税から贈与税として支払った分は控除されます。
※相続時に相続税額の方が少ない場合または相続税がかからない場合は、贈与税を支払った分の還付を受けることができます。
【特例を利用できる要件】
■贈与者が65歳以上の親で、受贈者20歳以上の子であること。
【申告】
■適用を受ける子供が、最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署に届出をしなければなりません。
「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
■添付書類は、以下のとおりです。
・受贈者の戸籍の謄本又は抄本
・受贈者の戸籍の附票の写し
(受贈者が20歳に達したとき(又は平成15年1月1日)以降の住所又は居所を証する書面)
・贈与者の住民票の写し
~~直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度~~
■平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、要件を満たした場合において、一定金額贈与税が非課税となります。
【特例を利用できる受贈者の要件】
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
a.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
b.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
c.贈与を受けた時に、日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が日本国内に住所を有している。
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
(3)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
(4)贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
【住宅取得等資金の範囲】
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
【居住用の家屋及びその増改築等の要件】
細かい要件がありますので、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
【非課税限度額】
■次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、次のとおりとなります。
(1)省エネ等住宅(注2)の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度となります。
a.平成24年のときは1500万円
b.平成25年のときは1200万円
c.平成26年のときは1000万円
(2)(1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度となります。
a.平成24年のときは1000万円
b.平成25年のときは700万円
c.平成26年のときは500万円
(注1)既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額になります。
(注2)「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
【申告】
■この特例を受ける場合でも贈与税の申告が必要です(もらった年の翌年の2月1日から3月15日まで)。
~~基礎控除の利用~~
■贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。
そこで、1年110万円ずつ贈与していけば、多額の財産でも贈与することが可能となるのです。
しかし、実は、このような贈与の繰り返しは、「連年贈与」と認定され、一時に贈与があったものとみなされ、多額の贈与税が課されてしまう可能性があります。
■そこで、連年贈与とみなされないために次のような対策をする必要があります。
1.贈与契約書をその都度作成する。
2.110万円を少し超えるだけの贈与を行い、その証拠を残しておく。また納税も行なう。
3.毎年一定額ではなく、違う額を違う財産で贈与する。つまり単発の贈与であることをアピールする。
このような対策をしても絶対課税されないとは限りませんが、少額の贈与を繰り返すのであれば、最低でもこの対策を しておくことをおすすめします。
2.遺留分
~~遺留分の基礎知識~~
■相続人である配偶者、子供、直系尊属(両親等)には、遺留分という「最低限遺しておくべき財産」
が法律で決まっています。これを遺留分といいます。
■遺留分の割合は下記のとおりです。
| 相続人が直系尊属(両親等)のみの場合 | 相続財産の3分の1 | |
| ・相続人が子のみの場合 ・相続人が配偶者のみの場合 ・相続人が配偶者と子の場合 |
相続財産の2分の1 | |
| 相続人が配偶者と直系尊属(両親等)のみの場合 | 相続財産の2分の1 | |
※兄弟姉妹は相続人にはなりますが、遺留分は有しません。
■遺留分を侵害する生前贈与は、遺留分を侵害する範囲内で無効ということになっていますので、基本的には遺留分を考慮して生前贈与を行なう必要があります。
しかし、遺留分を考慮しない生前贈与をすることも可能です。
遺留分を侵害する生前贈与があった場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分にあたる財産の返還を求めることができることとされています(これを、「遺留分減殺請求」といいます。
■なお、遺留分を有する人(遺留分権者)が遺留分にあたる財産の返還を求める「遺留分減殺請求」ができるのは、
生前贈与については、相続開始前1年以内のものに限られます。
しかし、当事者双方が遺留分を侵害することを知ってした生前贈与は一年前の日より前のものでも
遺留分減殺の対象となります。
また、相続人に対する生前贈与(特別受益)は1年内に限らず遺留分減殺の対象となります。
~~遺留分対策を考える~~
■例えば、相続人でない人へ生前贈与する場合は、遺留分減殺請求を受けるのは「相続開始前1年内」との制限がありますので、早めにしておくというのが一つの対策になるでしょう。
ただ、贈与契約をする双方ともが遺留分侵害の事実を知ってなした場合は、関係がありませんので、相続人でなくても内縁の妻等のへの生前贈与は1年以上前のものでも遺留分減殺請求をされる可能性は残ります。
■また、遺留分は、生前に放棄することができます。
家庭裁判所で推定相続人が放棄の手続を行なうことが必要となりますし、遺留分にあたる程度の生前贈与があったなどの事情がないと放棄の許可がおりません。
よって、特殊な場合でない限り、この手段はとりにくいと思われます。
■そこで、遺留分を無視することも一つの手段です。
生前贈与をして名義を変えてしまい、相続財産として残っていないということになれば、相続人もあきらめてくれる可能性もあります。
また、遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈または遺言による遺産分割方法の指定があったことを知ったときから1年間行使しないと時効により、遺留分減殺請求権が消滅し、請求できなくなります。
相続の開始等を知らないときでも相続開始から10年間経過すれば時効で消滅します。
さらに遺留分減殺請求は、金銭賠償でよいとされていますので、遺留分減殺請求を受けたら、その人の遺留分にあたる
金銭を遺留分権者に支払えばよいということになっております。
本来、遺留分を考慮して生前贈与を行なうべきですが、仕方ない場合もありますので、そのときは遺留分を無視した生前贈与もやむをえないということになります。